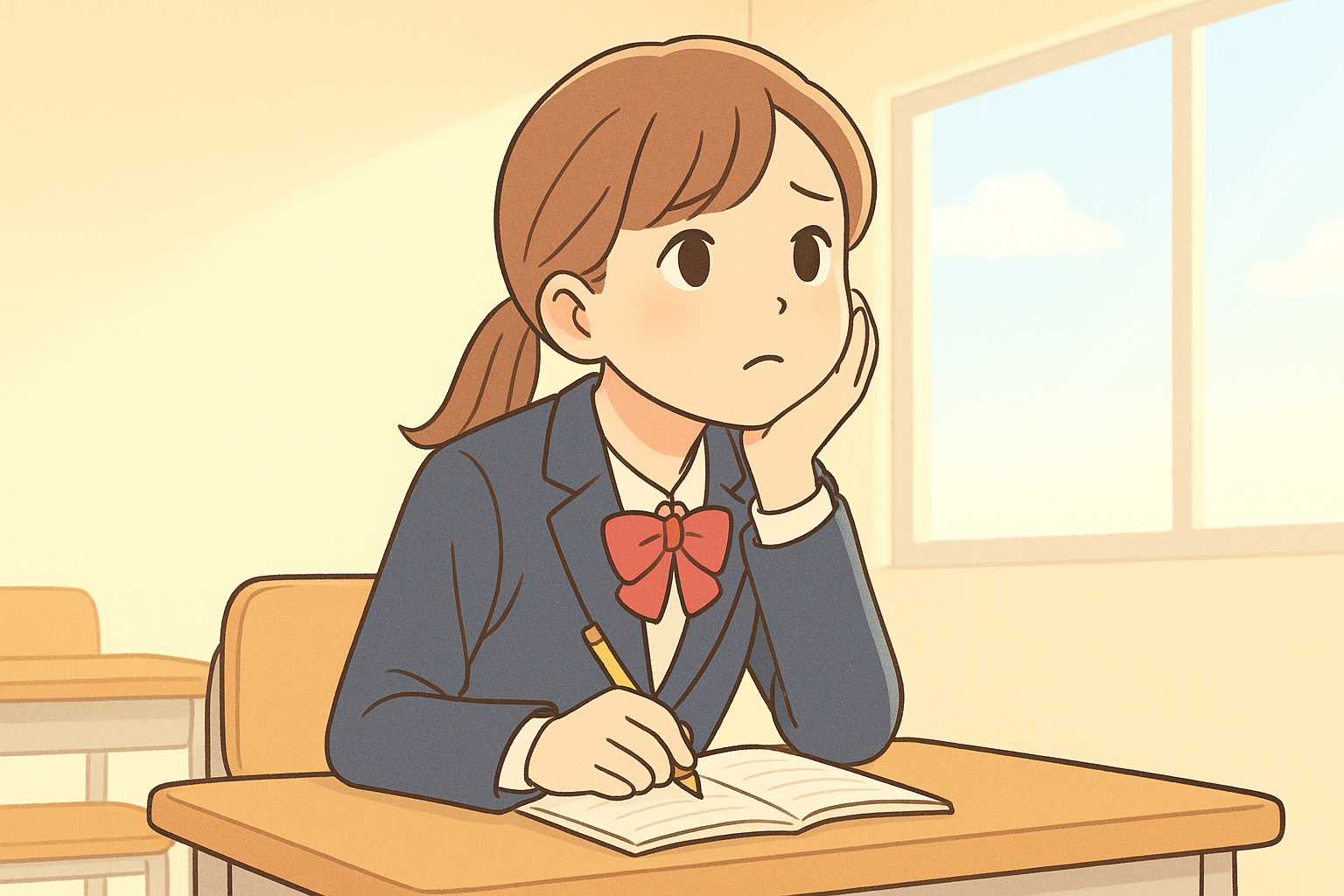保険って入るべき?

はじめて会社に保険の案内が届いたり、友人・知人から勧誘を受けたり、結婚や出産をきっかけに「やっぱり保険って必要?」と迷う方は多いはず。結論から言うと、保険は“誰にとっても同じ正解”はありません。
いまの自分の暮らし・家族構成・貯蓄力・将来の不安に合わせて、必要な保障だけを“選んで”備えるのが基本です。本記事では、迷いがちなポイントを整理し、あなたに合った考え方ができるように紹介します。
以前にも生命保険の相談のことについて紹介してますのでこちらもよければご参考に
記事はこちら
なんで保険に迷うの?
-
「なんとなく必要そう」というイメージが独り歩きしがち。
-
会社や営業からの案内で急かされて判断してしまいがち。
-
「入らないと不安、でも家計はきつい」──この板挟みがつらい。
迷いの正体は、保険の目的が曖昧なまま“良さそう”なパッケージを見ているから。まずは、自分は何を守りたいのか(誰の何のリスクに備えるのか)を言葉にしてみることが出発点です。
保険ってどんな種類がある?
保険は大きく分けて、「将来のため(準備)」と「万が一のため(保障)」に分かれます。
-
医療保険:入院・手術など医療費の自己負担や収入減少を補う。掛け捨て中心。
-
がん保険・三大疾病:治療の長期化・高額化に備える特化型。家族にがん罹患が多い等の事情があれば検討。
-
生命保険(死亡保障):万一のとき遺された家族の生活費・教育費を守る。独身か、扶養家族ありかで必要額は大きく変わる。
-
就業不能保険/所得補償:病気・ケガで働けない期間の収入を補う。
-
貯蓄型(学資・個人年金・終身など):将来資金を計画的に貯める目的。ただし手数料や途中解約リスクに留意。
目的が違えば、選ぶべき保険も変わります。まず「何に備える?」を先に決めるのがコツ。
保険は自分の未来への備え
若いうちは病気やケガの実感が湧かず、「いまは要らないかも」と感じがち。でも、若いほど保険料が安く、健康告知も通りやすいのは事実です。
-
自分のための視点:長期入院・通院で収入が減ったら?固定費は払える?
-
貯蓄とのバランス:3〜6か月分の生活費が貯まるまでは、掛け捨ての最低限の保障でつなぐ選択も現実的。
-
保険で貯めるは慎重に:積立は流動性(取り崩しやすさ)も大切。必要なら積立NISA等の資産形成と役割分担を。
「貯蓄のための保険」よりも、まずは“働けない・大きな医療費”という稀だけど重いリスクに薄く広く備える、が基本。
家族ができたら視点も変わる
自分一人の家計と、家族を守る家計では優先順位が変わります。
-
万一のとき誰が困る? 配偶者・子ども・住宅ローンの有無で必要保障額は変動。
-
目安として、死亡保障は**(生活費−遺族年金等)×年数+教育費+葬儀費**から逆算。
-
出産前後は医療・就業不能リスクも再点検。短期的には収入の穴をどう埋めるかが鍵。
家族の安心は「高額な保険」ではなく、“必要額に的確に届く設計”で実現します。
必要な保険だけで十分
パンフレットのパッケージ型は魅力的に見えますが、実は使わない特約(内容)が紛れやすいのも事実。
-
まずは公的保障(健康保険の高額療養費、傷病手当金、遺族年金)を把握。
-
その上で足りない分だけをピンポイントで追加する。
-
見積りは年額・通算負担で比較。月々数千円でも、10年で数十万円の差に。
保険は買うより設計する。不要な保障を削り、必要な保障に資源を集中させましょう。
焦らず、自分のタイミングで
保険はすぐに契約しなくてOKです。一度「目的→必要額→商品候補」の順で整理しましょう。
家計がカツカツなら、まず固定費の見直しと緊急資金づくりを優先することも重要です。
また、迷ったら第三者に相談をしてみてください。
私、よろず相談屋しおちゃんはFP資格保有してますし、保険業ではありませんので営業ノルマなしで“入らない”選択も含めて一緒に考えられますよ!
まとめ:あなたの安心設計をつくろう
保険は不安の全部を解決する魔法ではありません。でも、家計が受け止めきれない“大きなもしも”に橋をかける道具にはなります。大切なのは、
-
何に備えるかを言葉にする(目的)
-
公的保障と貯蓄で足りない“穴”を見つける(必要額)
-
その穴だけを、無理のない保険で埋める(設計)
この順番で考えれば、広告や勧誘に振り回されません。あなたと家族の安心にちょうどよい保険を、いまの暮らしに合わせて選びましょう。